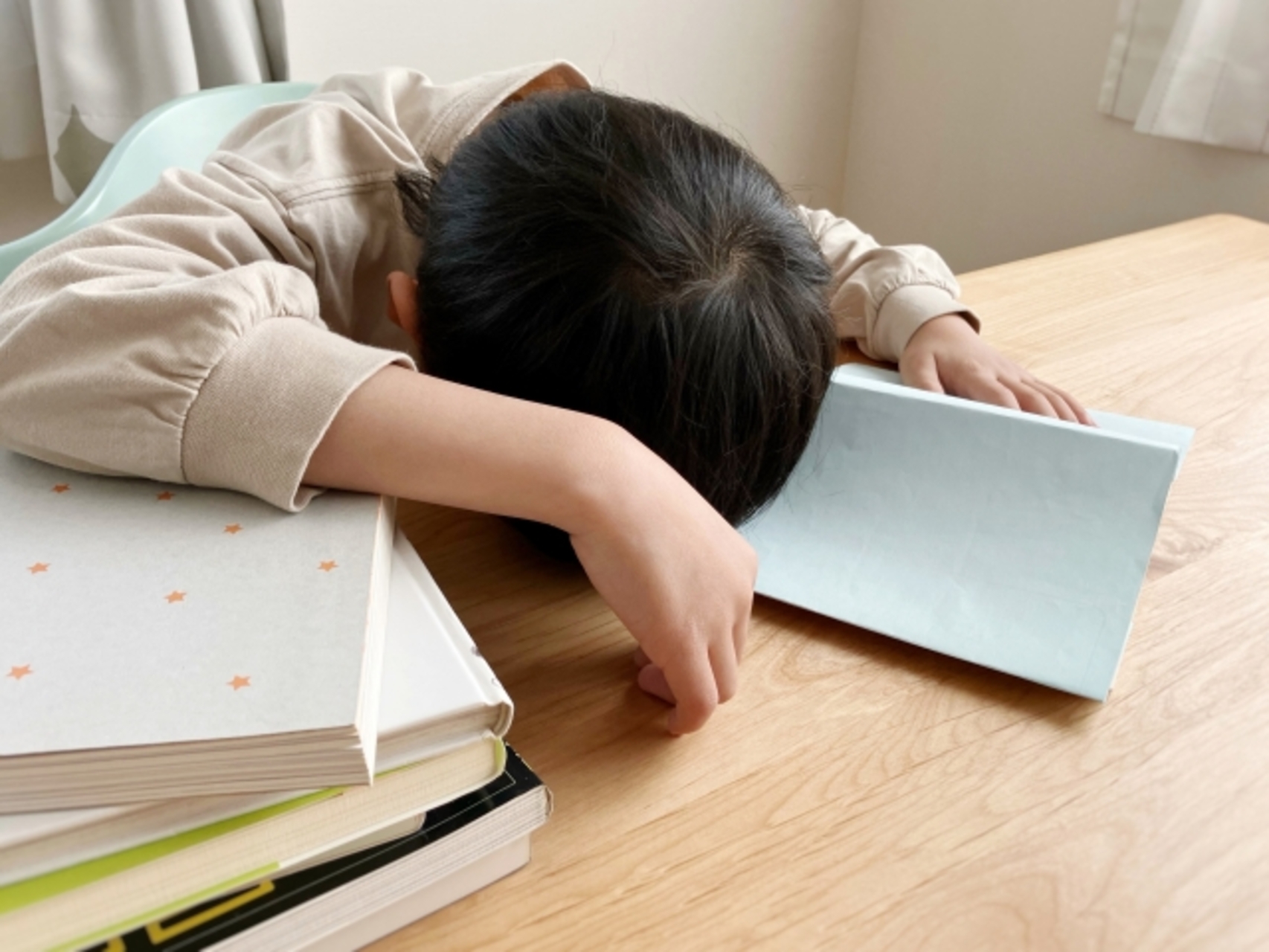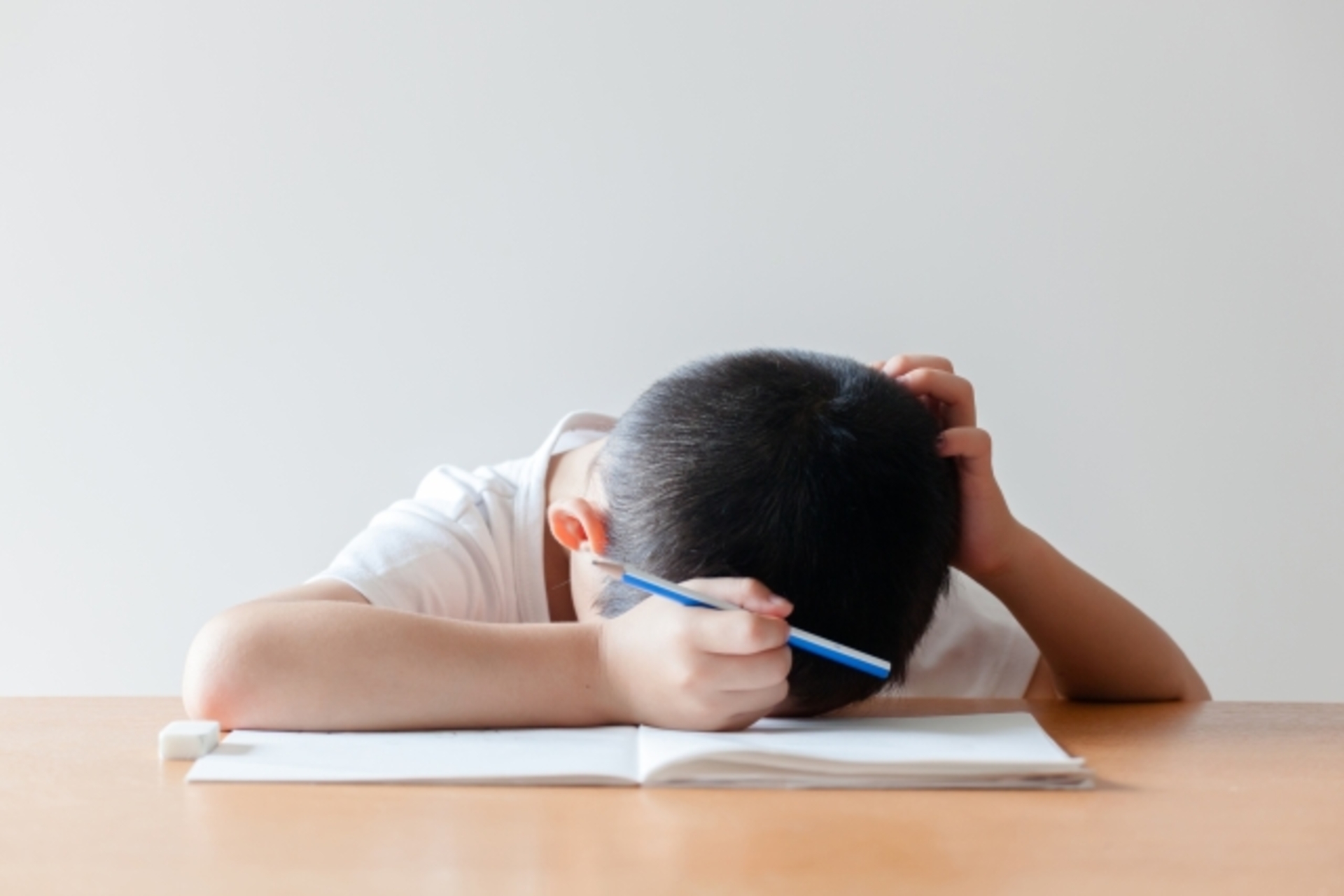神戸連続児童殺傷事件から28年。子どもたちの未来を守るために
1997年、私はまだ学生でした。テレビで繰り返し報道された神戸連続児童殺傷事件のニュース、今でも怖かったことを覚えています。幼い命が奪われた悲劇、犯人の少年の背景、そして社会全体に漂う無力感。あの衝撃的な映像と報道は、子どもながらに私の心に深い傷を残しました。
あの日の記憶は、今も私の中で生き続け、子どもたちの安全と未来を考える原動力になっています。
執筆 元警察官 安井かなえ
目次
事件が映し出した社会の闇

当時、ニュースを通して神戸の事件を知った私は、社会の闇を垣間見たような衝撃を受けました。ドラマではない、現実の世界で恐ろしいことが起きたのだと。
犯人の少年の心の歪みや家庭環境の問題、そして社会全体が抱える複雑な背景。それらは報道だけでは見えてこない部分でした。警察官になった私は、事件の裏に潜む根深い要因の数々を、現場で痛感しました。
子どもが犠牲になる事件ほど心が痛むものはありません。加害者、被害者、そしてその家族それぞれの人生が複雑に絡み合い、悲劇を生み出す現実を目の当たりにしてきました。感情をどこにぶつけて良いのかわからず気が動転する人々を何度も見るたびに、警察官として人々にどう向き合うかを考えさせられました。
そして今、母として我が子を抱きしめるたびに、あの事件で失われた幼い命の重さを改めて感じます。わが子の笑顔を守りたい。二度とあんな悲劇を繰り返したくない。その思いが、私を突き動かしています。元警察官としての経験と、母としての愛情を胸に、子どもたちの安全のためにできることを日々考え、行動しています。
安全を守る具体策

これまでの経験で培った「危険を察知する力」「状況を冷静に判断する力」そして「人の心を読み解く力」は、子育ての場面で役立つこともあります。事件捜査の現場で学んだ教訓を、母としてどう活かすか。子どもを守るための具体的な対策を紹介します。
地域との絆、子どもを見守るネットワークを築く
警察官時代、地域住民との連携が犯罪抑止にどれほど重要かを学びました。防犯パトロールを通じて、住民との情報交換は、子どもたちの安全にも繋がります。
現在では、母として地域の子育てイベントを主催したり、自治会と積極的に関わり、子どもたちをどのように見守るかを試行錯誤しています。また、朝の登校時の旗振り当番にも積極的に参加しています。
不審者情報や地域の変化を迅速に共有することで、子どもたちを守る「見えない防壁」を築くことが大切だと感じています。
家庭での安全対策、小さな習慣で大きな安心を
交番に勤務していた時代には「巡回連絡」やパトロールを通じて地域の家庭を訪問し、住民と会話してコミュニケーションをとり、防犯のアドバイスをする機会も多くありました。その経験から、我が家では鍵の管理や窓の施錠、防犯ブザーの携帯、不審者対応などを、子どもの年齢に合わせて教えています。危機管理のできている家庭では、制服姿の私を見て「本当に警察官ですか?」と質問する人もいました。
その時は、「この警察手帳が本物かどうかも見分けがつかないと思うので、もし不安でしたら警察署か交番に一度連絡して確認してみてください」と声をかけていました。
ネットの危険から子どもを守る
今の子どもたちは、デジタルネイティブ世代とも呼ばれ、スマートフォンやSNSを通じて、私たち親世代とは異なる新しいリスクにさらされています。そのため、子どもにネットリテラシーを徹底的に教えていくためには、親であるわたしたちも、学び続ける必要があると思います。
SNSにある危険性を、子どもが理解できる言葉で説明し、ルールだけでなく「なぜそれが大切か」を伝えるようにしています。
また、定期的に子どものネット利用状況や、どのようなアプリをダウンロードしているのかを確認しつつ、気軽に話せる雰囲気を作ることで、トラブルを未然に防ぐ努力を続けています。
私自身では、ネットリテラシーを遊びながら学べるイベントを開催するなど、ネットリテラシー教育をもっと身近に感じてもらいたいと思っています。
子どもの心に寄り添うために

たくさんの少年補導を経験するなかで、補導や犯罪の背景には家庭や学校での悩み、心の傷が深く関わっていることを学びました。特に印象的だったのは、補導をした少年の親に連絡を取っても「うちは関わりたくない」と我が子を平気で突き放す親がとても多かったこと。その現実に衝撃を受けました。
子どもは、言葉にできないストレスや不安を抱えていることがあります。だからこそ、小さなサインを見逃さず、心の声に耳を傾けることが大切だと痛感しています。
心を開くコミュニケーション
子どもが何でも話せる環境を作るため、日常の小さな出来事にも耳を傾け、共感することを心がけています。「今日、学校で何が楽しかった?」と聞くだけでなく、子どもの表情や声のトーンから気持ちを読み取り、安心して話せる雰囲気を作るよう努めています。小3の息子は、最近「面倒くさいなぁ」という表情を浮かべるようになってきましたが、それでも学校でのできごとを話してくれます。
子どもが心を開いてくれる瞬間は、どんな小さな会話からも生まれると感じています。
感情を受け止める
子どもが怒ったり悲しんだりしている時、頭ごなしに否定せず、まずはその気持ちを受け止めることを大切にしています。「そうか、悔しかったんだね」と共感することで、子どもは自分の感情を整理し、安心感を得られます。感情の背景を理解しようとする姿勢が、子どもの心を支える第一歩です。
専門家の力を借りる
親だけで解決するのが難しい悩みもあります。子どもの様子に異変を感じた時、スクールカウンセラーや児童相談所、心理士(心理相談室)などに相談してみましょう。専門家の視点は、子どもの心の傷を癒し、親としてどう支えるかのヒントをくれます。
地域と手を取り合う

時代が変わっても、犯罪防止には地域の力が欠かせません。防犯には、警察・学校・地域住民・家庭が一体となって子どもを見守る環境を作ることで、初めて安心できる社会が築けます。
地域イベントでつながる
地域のイベントやボランティアに参加することで、近隣の人たちと顔見知りになり、子どもたちを見守る輪が広がります。子どもたちも「この地域には見守ってくれる大人がいる」と感じ、安心して過ごせるようになります。
私の住む地域には「だんじり」という伝統的なお祭りがあるため、大人と子どもの交流や地域の人たちと顔見知りになるきっかけ作りが容易にできています。
お住まいの地域の状況にもよりますが、地域とつながるきっかけを探してみてくださいね。
まとめ
・神戸の事件を忘れず、悲劇を繰り返さないという強い使命感
・家庭・地域・社会が一体となった子どもの見守り体制の重要性
・子どもの心に寄り添い、感情やSOSを見逃さない姿勢の大切さ
子どもが被害に遭う事件は、私たちに深い悲しみと、決して忘れてはならない教訓を残しました。この悲劇を決して風化させず、子どもたちの安全を守る努力を続けることが、私たち大人の責任です。
-3.png)
安井かなえ
元警察官
小学生と幼稚園児までの3人の子どもの肝っ玉母ちゃん。警察庁外国語技能検定北京語上級を持つ。 交番勤務時代に少年の補導や保護者指導を経験後、刑事課の初動捜査班で事件現場に駆けつける刑事を経て、外事課では語学を活かし外国人への取り調べや犯罪捜査などを行う。 現在は、防犯セミナー講師として企業や市民向けに活動中。 好きな音楽はGLAY。