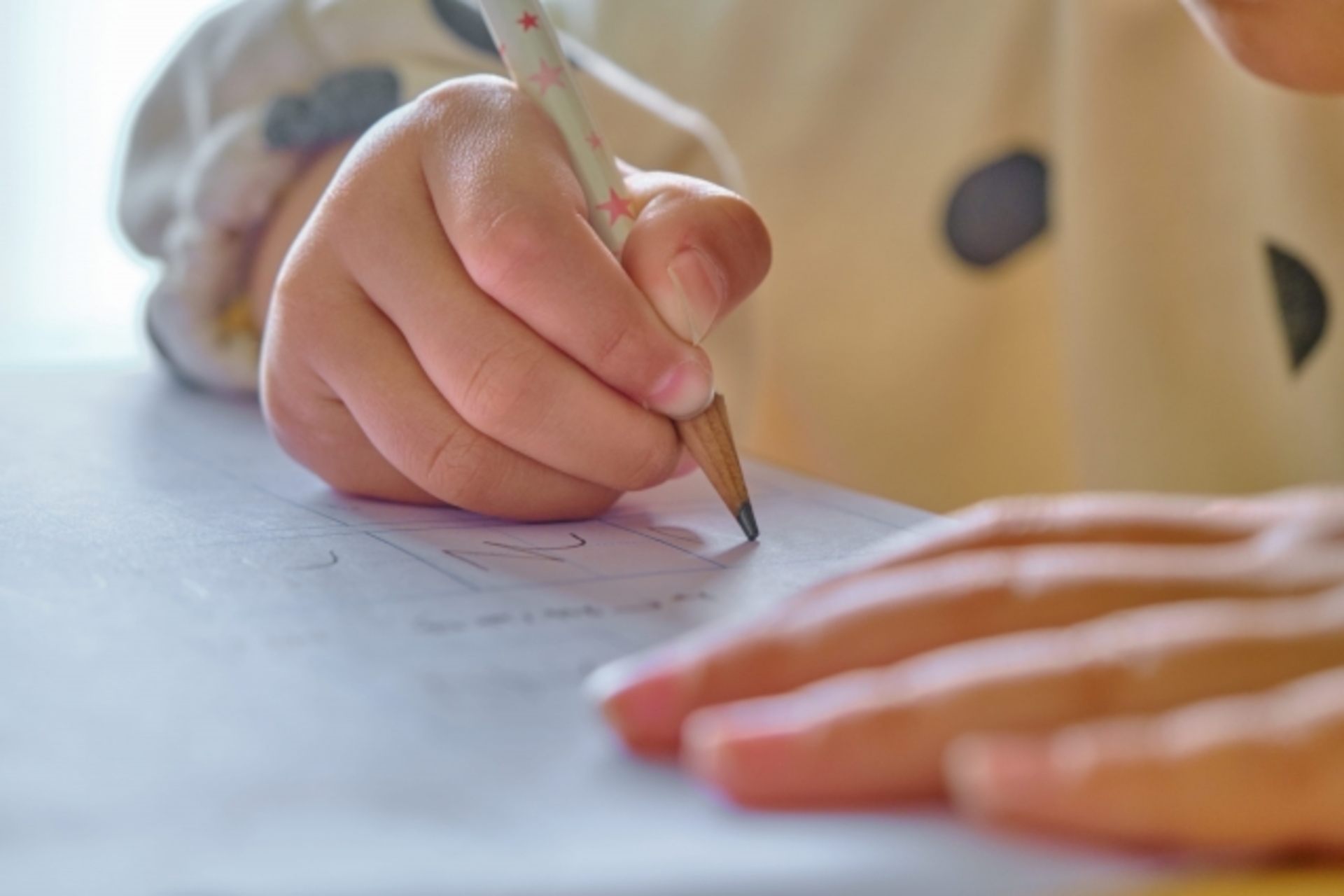男の子も標的!子どもの性被害の現状と親が知っておくべきこと
「まさかうちの子が」「男の子だから大丈夫」そんな思い込みが、子どもたちを危険にさらしているかもしれません。性被害は決して他人事ではありません。そして、被害者は女の子だけではないのです。
執筆 元警察官 安井かなえ
目次
「男の子の性被害」はなぜ見過ごされがちなのか

多くの人が「性被害=女の子の問題」と考えがちですが、これは大きな誤解です。男の子の被害が見過ごされやすい理由は大きく3つあると考えています。
1.男の子自身が被害を理解できていない場合が多いこと
2.「男の子が性被害に遭うはずがない」という社会の偏見により、周囲の大人が兆候を見逃してしまうこと
3.男の子特有の「恥ずかしさ」や「男らしさ」への圧力により、被害を訴えにくい環境があること
私自身、捜査の現場で痛感したのは、被害者の家族が「なぜうちの子が」と冷静ではいられず、子どもへの接し方を誤り、子どもが悪いと責めたり、根掘り葉掘り聞き出そうとして心の傷を深くしてしまうケースをたびたび目にしてきました。
性被害は発覚が遅れるほど、子どもへの影響は深刻になります。早期発見、早期対応のためには、まず私たち大人が「男の子も性被害の被害者になりうる」という現実を正しく理解することが不可欠です。
性被害の実態を数字で知る

警察庁の最新データによると、2024年の18歳未満の子どもの性犯罪検挙件数は男女合わせて4,850件となり、過去10年で最多を記録しました。
特に深刻なのは、SNSを介した犯罪被害です。小学生の被害者数は2024年に136人となり、2015年の35人から3倍以上に増加しています。
さらに衝撃的なのは、日本財団の調査によると、日本では推定で年間約39万人もの子どもが性被害に遭っており、これは1日あたり約1,000人以上にのぼります。
この数字は氷山の一角であり、実際の被害はより深刻である可能性が高いとされています。警察庁の統計を見ても、性犯罪は確実に増加傾向にありますが、その背景にはこれまで隠れていた被害が「見える化」されてきた側面が大きいと考えられます。
警察庁の調査では、性暴力被害者の約1割が男の子であることが明らかになっています。少数に見えても、決して軽視できない数字です。
小学生の被害で特に深刻なのは、自分が被害を受けていることを理解できないまま、長期間にわたって被害が継続してしまうケースです。また、信頼していた大人から被害を受けることで、人間関係の基本的な信頼感に深刻な影響を与えることも少なくありません。
男の子も性被害の標的になる理由

性犯罪者が子どもを標的にする理由は、必ずしも性的な動機だけではありません。子どもの純真さ、従順さ、そして何より「力の差」が加害者にとって都合が良いのです。男の子も女の子も、大人に比べれば圧倒的に弱い立場にあることに変わりはありません。
加害者は巧妙に子どもに近づきます。優しい言葉をかけ、特別扱いをし、段階的に不適切な行為に慣れさせていく「グルーミング」という手法がよく使われます。この手段を使われると子ども自身が「悪いことをされている」と認識することが困難になってきます。
男の子が性被害を受けた場合の心理的影響には、独特の側面があります。「男らしさ」を求められる社会的圧力の中で、自分が「弱い立場」に置かれたことへの劣等感や自己否定感が強く現れることがあります。
また、身体的な反応があった場合、それを「自分が望んでいたのでは」「自分にも責任がある」と誤解してしまうことも多いのです。
親ができること、日常の対策

まず重要なのは、性被害は「特別な家庭の特別な子ども」に起こることではないと理解することです。どんなに注意深い親でも、24時間子どもを見守ることはできません。完璧な予防は不可能だからこそ、早く異変を察知することが大切だと思います。
日頃のコミュニケーションが最も重要な防御策
「今日は誰と遊んだの?」「なにか嫌なことはなかった?」といった何気ない会話を大切にしてください。ただし、矢継ぎ早に質問したり、尋問のようになってはいけません。子どもが自然に話せる雰囲気作りを大切にしてください。
親は、男女関係なく子どもに対して「君の体は君だけのもの」「嫌だと思ったら『嫌』と言っていい」「秘密にしようと言われても、お父さんお母さんには何でも話していい」ということを繰り返し伝えましょう。「男の子だから強くなければいけない」「男の子は泣いてはいけない」といった固定観念は、被害の発見を遅らせる原因となります。むしろ「困ったときは助けを求めることが大切」「あなたを守りたい大人がたくさんいる」ということを伝えてください。
変化に気付くポイントとして、急に内向的になった、部屋に閉じこもるようになった、特定の場所や人を避けるようになった、睡眠や食欲に変化がある、年齢に不相応な性的な知識や行動を示す、などがあります。
ただし、これらの変化が必ずしも性被害を意味するわけではありません。大切なのは、変化に敏感であると同時に、冷静に対応することです。
年齢に応じた適切な性教育
小学校低学年でも理解できるよう、「プライベートゾーン(水着で隠れる部分)は他の人に触らせない」「もし触られそうになったら大きな声で『やめて』と言って逃げる」ことを教えましょう。
また、インターネットを通じた被害も増加しています。オンラインでも知らない人とのやり取りには十分注意し、写真の送信要求などには応じないよう伝えましょう。
中には嫌がる子どもがいるかもしれませんが、親もときどきスマホをチェックさせてもらうなど、家庭内でのルールづくりも大切です。
まずは誰かに相談を

以前に比べ、子どもの性被害に関する相談窓口は徐々に整備されてきています。児童相談所、警察の被害者支援室、民間のサポート団体など、さまざまな選択肢があります。しかし、まだまだ利用しやすさや専門性には課題が残っています。
特に男の子の被害者に対するサポート体制は、女の子に比べて遅れているのが現状です。カウンセラーや支援者の中にも、男の子の被害への理解が十分でない場合もあります。
【被害が疑われる場合の相談窓口の例】
・児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)
・性暴力に関するSNS相談「Curetime」
・各都道府県の犯罪被害者支援センター
相談することで「大げさではないか」と心配する必要はありません。専門家が適切に判断し、必要な支援につなげてくれます。また、PTA活動や地域の防犯活動へ積極的に参加したり、学校での安全教育への協力など、親としてできることは多くあります。
まとめ
・男の子も性被害の標的になる。 「男の子だから大丈夫」という思い込みは危険
・日常のコミュニケーションと性教育で信頼関係を築き、子どもが安心して話せる環境をつくる
・迷わず専門機関に相談し、地域や周囲と連携して子どもを守る
子どもの性被害という現実は、確かに重く、できれば考えたくない問題です。しかし、目を逸らすことで守れるものはありません。むしろ、正しい知識を持ち、適切に備えることで、子どもたちをより確実に守ることができるのです。
この記事が、一人でも多くの親御さんの意識を変え、一人でも多くの子どもたちを守ることにつながることを心から願っています。
-5.png)
安井かなえ
元警察官
小学生と幼稚園児までの3人の子どもの肝っ玉母ちゃん。警察庁外国語技能検定北京語上級を持つ。 交番勤務時代に少年の補導や保護者指導を経験後、刑事課の初動捜査班で事件現場に駆けつける刑事を経て、外事課では語学を活かし外国人への取り調べや犯罪捜査などを行う。 現在は、防犯セミナー講師として企業や市民向けに活動中。 好きな音楽はGLAY。