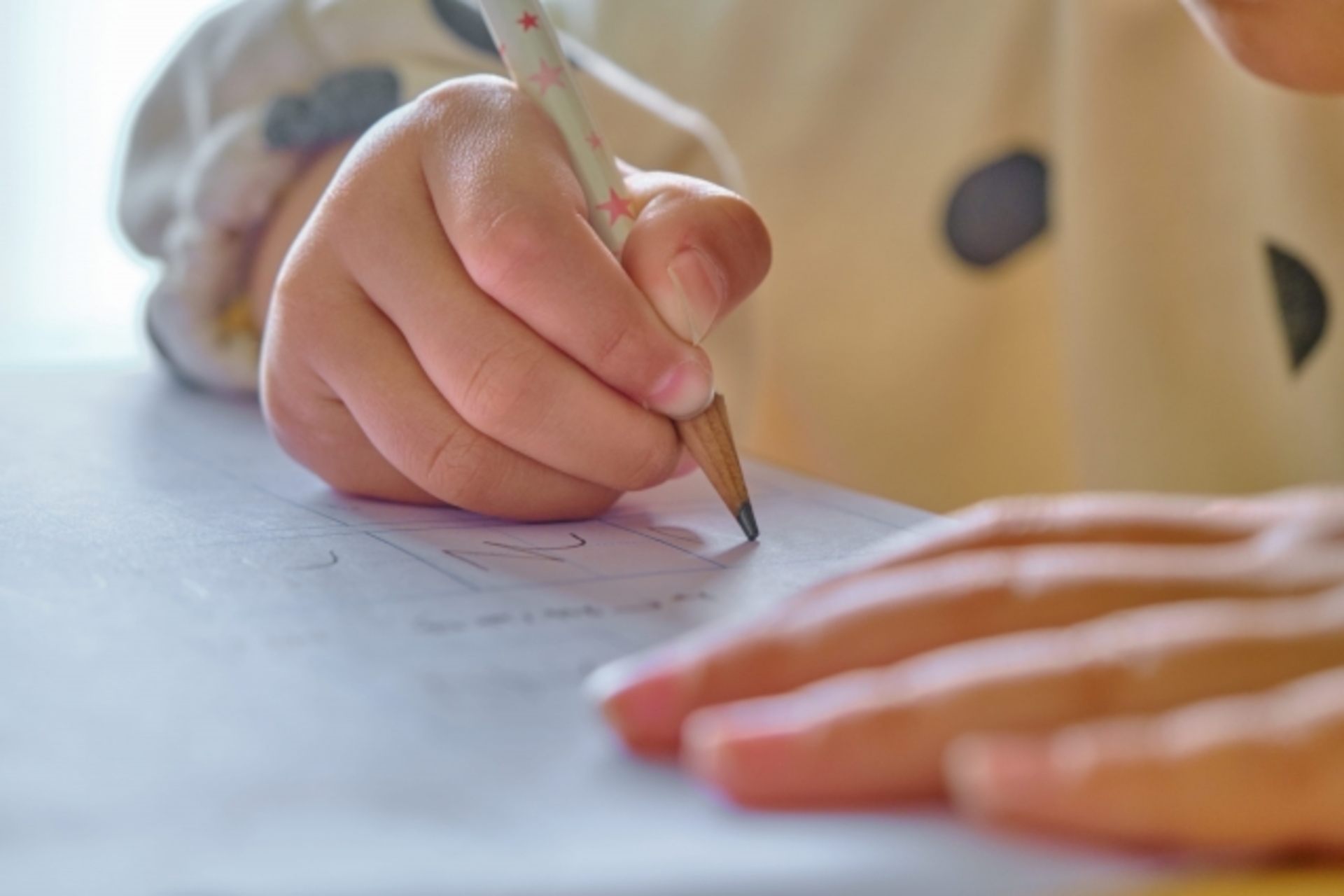子どもの写真をSNSに投稿する前に!安心安全な写真共有術
日々の子育ての中で、子どもの可愛い瞬間を写真や動画に収めてSNSにアップロードしたくなる気持ち、よくわかります。私も同じように我が子の成長を残したいと思う一人です。しかし、ネット上に子どもの写真を投稿することには、思っている以上の危険が潜んでいることをご存知でしょうか。
SNSは簡単に情報を共有できる反面、その裏には私たちの想像をはるかに超えるリスクがあります。今回は子どもの写真をSNSに投稿する際に気をつけるべきポイントと、すぐに実践できる具体的な対策を解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、安心して子どもの思い出を残せる環境づくりに役立ててください。
執筆 元警察官 安井かなえ
目次
SNSにおける子どもの写真悪用の現状

警察庁の統計によると、2024年には、児童ポルノ関連の事件の中で「児童自らが撮影した画像に関係する被害」が462件検挙されています[a]。しかし、これは摘発された一部の数字に過ぎず、発覚していない事件や隠された被害はそれ以上に多いと考えられます。
たとえ一見無害に見える写真でも、背景や服装、小物、投稿コメントなどから簡単に個人情報を割り出すことが可能なのです。こうした情報が悪用され、子どもたちはストーカー被害や予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクを抱えているのです。
写真には個人情報が詰まっている

SNSに投稿された写真には、気づかぬうちに住所や学校、氏名などの個人情報が写り込んでしまうことがあります。たとえば、自宅の外観や表札、学校の看板、近所の公園やお店の名前、さらには特徴的な建物の壁などは、個人を特定する手掛かりとなってしまいます。
また、Googleの画像検索を使えば、特徴的な場所であれば番地まで簡単に特定できてしまうこともあります。
さらに、近年のAI技術の急速な発展により、子どもの写真が悪質に加工されるリスクも深刻化しています。何気ない写真が、性的な画像に改変されネット上に拡散されてしまうケースも頻繁に発生しています。
こうした事態を受け、2025年7月、政府はAIによる人権侵害のリスク調査[b]に乗り出し、社会全体でこの問題に対処しようとしています。しかし、一度拡散した情報は完全に消すことが難しく、子どもたちの将来に重大な影響を及ぼす可能性があります。
隠された危険「ALT属性」の悪用に注意

ALT属性という言葉をご存知でしょうか?ALTとはウェブサイトやSNSで使われる「代替テキスト」のことで、画像にカーソルを合わせたりスマホでタップしたりすると表示される説明文のことです。
本来は視覚障がい者のために画像内容を説明する目的で使用されますが、近年では、このALT属性が思わぬかたちで“悪用”されるケースが出てきています。
たとえば、「クリックしてね」などとALTに書き見た人を意図的に誘導しようとする悪質な使い方や最近では子どもたちが遊びの感覚で、ALT内に情報を書き込むことが流行しており「行った場所」「名前」「住所のヒント」などを書いてしまうことがあります。
親が知らない合言葉や住所の詳細なども隠される可能性があるため、ALTテキストの管理も忘れてはいけません。一見安全そうに見える写真でも、ALTに隠された情報が子どもたちを危険にさらすリスクをはらんでいるのです。
ALT悪用の2大パターン
1. うっかり書き込み型(無意識の危険)
子ども自身や親が、ALT欄に「今日は◯◯公園に行ったよ」など、無意識に個人情報につながる内容を入力してしまうケース。
2. 意図的な誘導型(悪意ある操作)
「クリックしてね」「このリンクを見て」など、一見無害に見える言葉をALTに仕込み、ユーザーの行動を意図的に誘導する手口。
どちらも、一見しただけでは気づきにくいのが特徴です。だからこそ、画像を投稿する前にALT欄を必ず確認することが大切です。もし自動でテキストが入っていたら削除しましょう。また、ALTを使う場合でも、個人情報や位置情報、誘導文のような内容は書かないように心がけてください。
SNSに投稿する際は、キャプションだけでなく「見えない部分=ALT属性」もチェックすることが、子どもを守るためにとても大切です。
子どもの写真を安全に共有する3つの柱

子どもの写真をSNSで安心して共有するために、特に気をつけるべき3つのポイントをご紹介します。
1. 背景・服装・キャプションのすべてで個人情報を守る
写真の背景に写り込む自宅の外観、表札、学校の看板、近所の公園やお店の名前、特徴的な建物やビルは、住所を特定されるリスクが高まります。撮影前には必ず背景を入念に確認し、個人情報が写り込んでいないか確かめましょう。
また、スマホに自動で付与される位置情報(ジオタグ)は必ずオフにしてください。子どもの顔はモザイクやぼかしでしっかり加工しましょう。無料アプリの「PicsArt」などを活用すれば簡単に加工できます。ただし、黒ペンでの塗りつぶしは明るさ調整で露出してしまうことがあるので避けてください。
2. 露出度の高い服装やポーズは避ける
水着や下着など露出度の高い服装は、性的な対象として悪用される危険が非常に高く危険です。自宅やプライベートな場面でも、ネットに投稿する際は慎重になりましょう。
近年、SNS上で「キッズモデル」を名乗り、子どもの水着姿を有料で撮影させ、また親が子どもの高い露出度の写真を投稿してSNSの反応を利用し利益を得ようとするケースが批判されています。
子どもの同意を得ているとはいえ、18歳に満たない子どもの権利を軽視し、性的搾取につながるリスクもはらんでいるとして問題になりました。
親は子どもの写真投稿による報酬やいいね数(エンゲージメント)を目的としがちですが、その結果炎上し、子ども自身の将来に大きな悪影響を及ぼすこともあるのです。
3. キャプションに個人情報を書かない
投稿時の文章(キャプション)には、名前や年齢、学校名、通学路、習い事などの個人情報を一切書き込まないようにしてください。
一見無害な情報でも、犯罪者にとって住所特定や接触の足掛かりとなります。 代わりに、場所を示す際にランドマークなどを利用したり、顔全体が写っていない写真を選んだりするなど、工夫してみましょう。顔を隠しつつ、自宅から離れた場所や外出先のみの投稿もおすすめです。
プライバシー設定も適切に設定し、安全なSNS利用を心がけてください。
まとめ
・投稿する写真の背景や服装、キャプションには細心の注意を払う
・AIによる悪用リスクを防ぐため、写真の加工やALTテキストの管理を徹底する
・露出度の高い写真や動画の投稿は避ける
ちょっとした投稿でも、背景や文章、位置情報から個人が特定されてしまうことがあります。 子どもの裸や露出度の高い写真は絶対に避け、位置情報はオフにして、顔や特徴はぼかすなどの加工をしましょう。公開範囲も、本当に信頼できる人に限定するなど、慎重な対応が大切です。
子どもの大切な思い出を、安全に守りながら記録していきましょう。
-2.png)
安井かなえ
元警察官
小学生と幼稚園児までの3人の子どもの肝っ玉母ちゃん。警察庁外国語技能検定北京語上級を持つ。 交番勤務時代に少年の補導や保護者指導を経験後、刑事課の初動捜査班で事件現場に駆けつける刑事を経て、外事課では語学を活かし外国人への取り調べや犯罪捜査などを行う。 現在は、防犯セミナー講師として企業や市民向けに活動中。 好きな音楽はGLAY。