
小学生の宿題、いつまで、どこまで見る?自立への道筋は
小学校に入学して、早々に始まるのが「宿題」。なかなかゆっくり見る時間が取りづらかったり、どこまで口を出していいの?と疑問に思ったりするでしょう。ていねいに取り組むことで、学習の定着が期待できますが、子ども自身が宿題に苦手意識を持ってしまうのはもったいないことです。宿題の取り組み方について、一概に「これが正解」というものはありませんが、それぞれのスケジュールや子どもの性格に合わせた付き合い方が見つかるように、ご紹介していきます。
執筆 元教員 金島ちぐさ
目次
子どもの宿題「どこまで」見る?
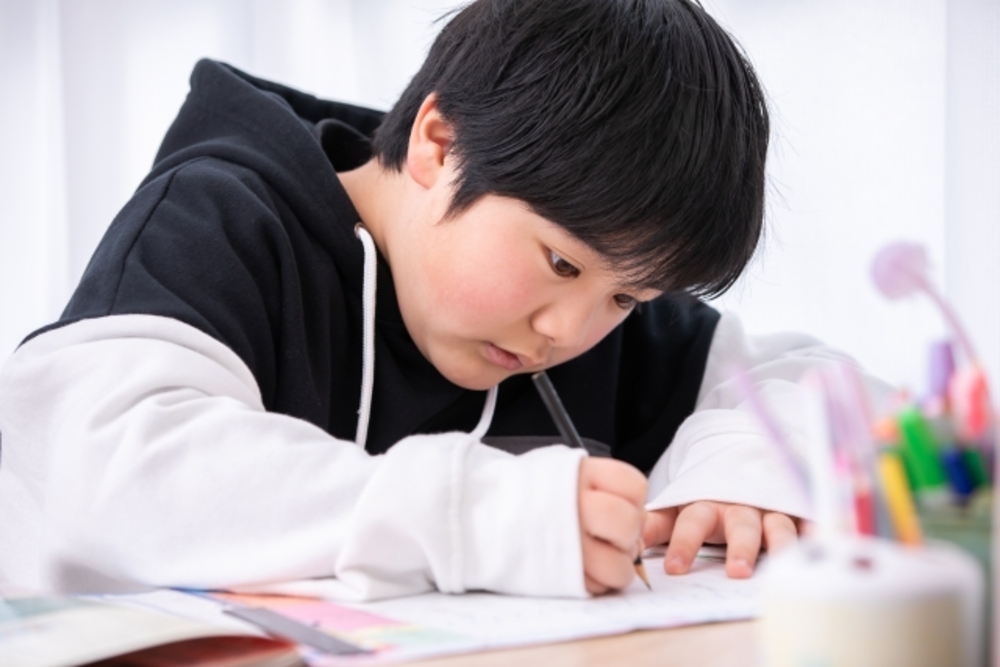
宿題の進め方には、間違いは学校で直せばいいと考える方もいれば、お直しまで家でやった方がいい。と考える方まで、宿題の取り組み方も家庭によってさまざまです。本人の性格や習い事の都合、家の事情がそれぞれありますから、まずは取り組むことを第一目標にして、余裕のある日はその先のフォローまでできるといいですね。
宿題をやるように声掛けをする
帰宅から宿題開始までのルーティンが決まっていればいいのですが、習い事などの都合で毎日一定に保つのも難しいことがあると思います。そんなときは、お風呂に入る前やゲームを始める前に「宿題やった?」と声掛けをしましょう。
宿題に対する姿勢は、「言われなくてもやる」子どもから「バレなければサボりたい」と思う子どもまで、性格によってそれぞれ取り組み方が異なります。まずは宿題を毎日コツコツ取り組めるようになることが目標です。
やったかどうかの確認をする
声掛けのみから1歩進むなら、宿題をやったかどうかの確認をしてみましょう。学童に通う子は学童で宿題をするので、その確認がしやすくなります。連絡帳、学校からの手紙、宿題の3つをまとめて親に見せる習慣が身につけば、確実に宿題に取り組んでいるかが把握できます。
学校からの宿題も毎日決まったものが出るとは限りません。計算ドリルの日もあればプリントの日もありますし、低学年であれば日記、高学年であれば自主学習など、その日によって内容が異なります。持ち物の確認も含めて、連絡帳と合わせて確認するのがおすすめです。
丸付け(正誤確認)をする
漢字やふりがなが合っているか、計算が合っているかの確認をすると、子どもの学習の理解度が分かってきます。毎日は難しくても、できるタイミングで、宿題の内容に目を通したいですね。
ただ、ここで「やり直し」を多くさせすぎると、子どものやる気をそいでしまう可能性があります。特に漢字の宿題はきれいな字で書いてほしくなりますが、まずは「正しく書けているか」に着目することがポイントになります。
苦手な問題のフォローをする
子どもが「間違った問題を直したい」「苦手を克服したい」「きれいな字を書きたい」といった気持ちをもっているときは、フォローのチャンスです。宿題で間違っているところを直したり、宿題外で問題を作ってみたりすると、学習の定着が図れます。しっかりとした問題は作れなくても、たし算やかけ算であればクイズ感覚で取り組むことも可能です。机に向かうだけが勉強ではないので、車での移動中やお風呂の中など、隙間時間で少しずつ取り組めると、子どもの自信にもつながります。
「いつまで」見るかは、子どもの性格に合わせて

小さい頃から自立心の強い、いわゆる「しっかりタイプ」の子どもは、宿題にも一人で取り組みたいと思うようです。隣で見られていると緊張してしまう「繊細タイプ」の子どももいれば、逆に目を離すとすぐにサボってしまう「めんどくさがりタイプ」の子どもも。どんなスタイルで宿題を見守るかは、子どもの性格に合わせて選びましょう。
1年生の始めは、宿題の取り組み方からフォロー
1年生の始めは、「学校で勉強をすること」「家で宿題をすること」そのものにワクワクしている子どもが多い時期。学習内容につまずくこともまだ少ないので、今のうちに宿題の取り組み方を身につけておけると安心です。姿勢やえんぴつの持ち方が正しいか。漢字ノートや計算ドリルなど、出されたページを決められたやり方でできているか。まだ習いたてなので、美しくはなくても、ていねいな字で書けているか。こういったことをポイントとして抑えられるといいですね。付きっきりで見守るのが難しい場合は、リビング学習もひとつの方法です。
慣れたら最終チェックだけでも〇
宿題への取り組み方が身に付けば、最終チェックだけにしてもOK。中学年にさしかかってくると、横にべったりとついて見守られるのが嫌になってくる子どもも増えます。また、「今日は友だちと遊びたいからサッと宿題を済ませよう」という日があったり、「今日は雨だし気分が乗らないからゆっくりでいいや」という日があったり、子ども自身も自分の気分の波に合わせた取り組み方をするようになってきます。宿題の時間が苦痛にならないような見守りをしたいですね。
高学年になるにつれて、聞かれたときだけ答えるスタイルに
高学年にさしかかってきたら、中学校やその先のことを踏まえ、勉強も少しずつ自立が必要になってきます。自分で取り組み、自分で見直す、そして正誤の確認をするところまで、1人で通してやる経験も大切です。ただ、子どもが勉強についていけているのか不安になることもありますよね。「今どんなことやってるの?」という会話をきっかけに、時折宿題やノートを見せてもらうのがおすすめ。あまりにも字が乱雑だったり、計算ミスが多かったりするようであれば、フォローのチャンスにもなります。
宿題とは関係なく、勉強内容について質問されたら、なるべくその場で答えられるといいですね。例えば、わが家の小6の娘も時々「今日の算数、全然分からなかった…」と言って帰ってくることがあります。そんなときは、授業でやった問題をもう一度解き直したり、次の授業の予習をしたりすることで理解を深めています。
「分からないことは先生に聞いてね」もOK
子どもが勉強につまずいたら、なるべく助けてあげたいですよね。でも親にも、得意不得意があります。うまく説明できないと思ったら、「明日先生に聞いてみてね」と伝えるのもOK。わたし自身も、小5のときに母から「悪いんだけど、もう宿題を見ても合ってるかどうか分からないや!」と明るく言われた記憶があります。
勉強はもちろん、大人になっても、「分からないことを人に質問する」機会は山ほどあります。質問をする練習にもなりますし、パパ・ママも「宿題を見てあげなきゃ!」と気負いすぎないようにしてくださいね。
まとめ
・声掛けをして習慣づける
・宿題をやったかのチェック
・丸付けを通じて、子どもの「苦手」と「得意」を理解する
・本人に合わせてフォローをしてあげる
小学生の宿題について、保護者の寄り添い方をご紹介しました。「ここまでやればOK」と言い切るのはなかなか難しいのですが、まずは毎日机に向かい、宿題に取り組む習慣を身に付けることが大切だと思います。子どもの性格や成長に合わせて、付き合い方を選んでいきましょう。
-1.png)
金島ちぐさ
元教員
国立大学の学校教育学部にて、小学校教員と中高音楽教員の免許を取得。卒業後は小学校の正教員として勤務。結婚を機に退職し、現在は小学生2人を育てながら教育・子育てに関する情報を発信している。










