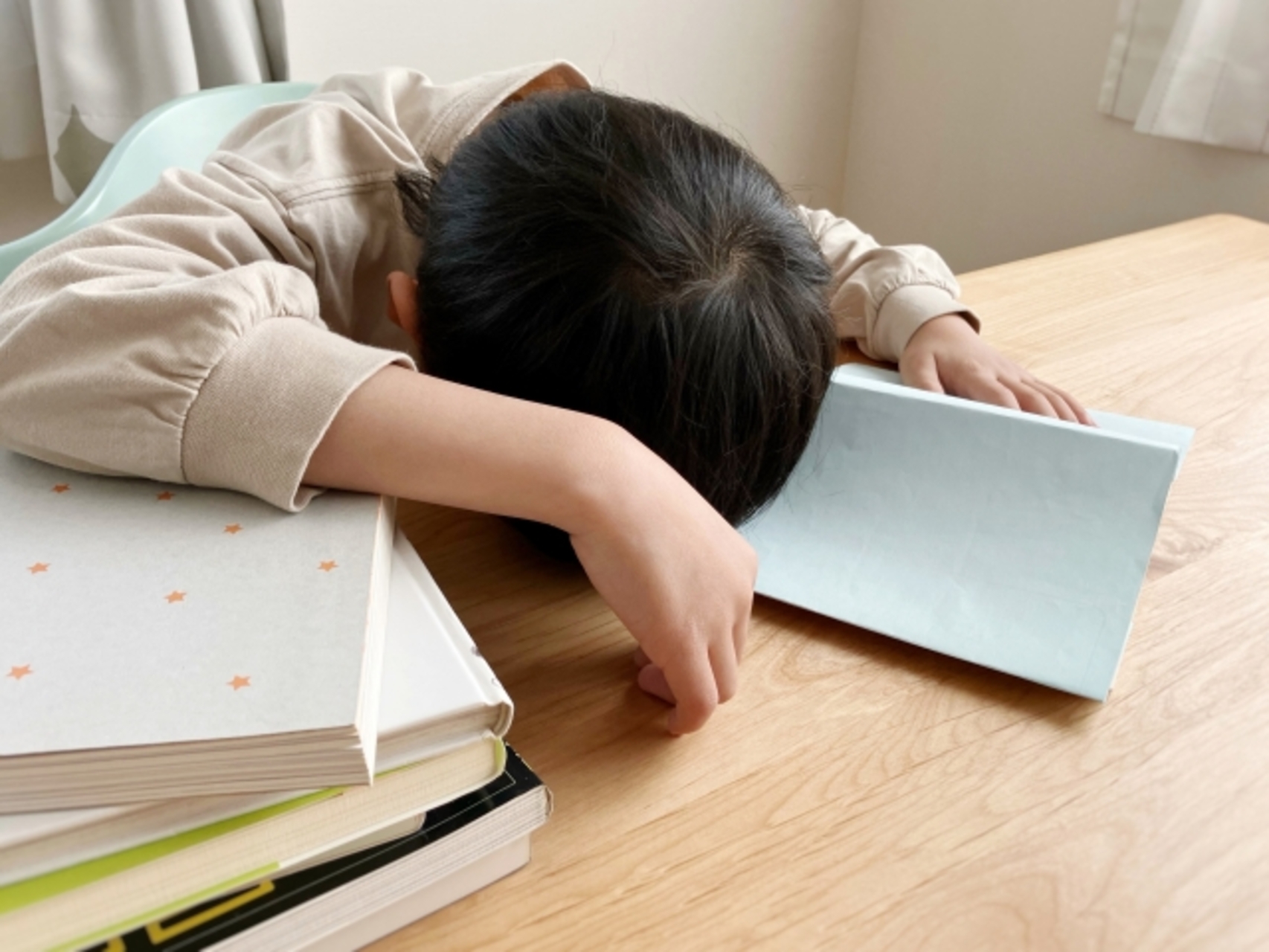都市型犯罪から子どもを守る!最新の安全対策とは?
都市型犯罪という言葉をご存じでしょうか。その名の通り、都市部に集中しやすい傾向の犯罪をいいます。都市部は人々が行き交い、人口も密集する犯罪が起こりやすいエリアです。近年、犯罪者の手口は年々巧妙化し、特に子どもを狙う犯罪が増加していることを痛感しています。
子どもの安全は、一人ひとりの努力と社会全体の意識によって守られます。一緒に、都市で起こりうる危険と向き合い、子どもたちを守る知恵を学んでいきましょう。
執筆 元警察官 安井かなえ
目次
都市部特有の子どもを取り巻く危険

都市部は匿名性が高く、人の出入りが激しい環境。犯罪者にとって、絶好の場所なのです。人混みに紛れやすく、逃走経路も多様。駅や商業施設、公共交通機関は、子どもが狙われやすい場所のひとつです。
特に危険なのは、監視の目が届きにくいデッドスペース。エレベーター、駐車場、人通りの少ない路地、公園の死角、公衆トイレなど。どんな場所でも死角があれば、そこはもはや犯罪者が潜伏しやすい、子どもを狙うのに格好の環境となってしまうのです。
さらに、デジタル技術の発達により、SNSや位置情報を悪用した新たな犯罪リスクも増えています。子どもの行動が追跡され、個人情報が簡単に収集される危険性があります。匿名性の高いはずのインターネット空間も、大きな脅威となっているのです。
最新の都市型犯罪トレンド

犯罪者の手口は日々進化し、従来の犯罪では考えられなかった巧妙な犯罪手法が使われています。特に近年目立つのは、テクノロジーを駆使した犯罪の増加です。
SNSを通じた声かけ、位置情報の追跡、偽のプロフィールを使ったアカウントによる誘い出しなど、デジタル空間での犯罪が急増しています。子どもが気づかないうちに個人情報を収集され、信頼関係を装って接近する手口が増えています。
従来の「つきまとい」犯罪も進化しています。ターゲットにされた子どもの行動パターンを綿密に分析し、タイミングを計算した接触が増加しています。例えば、通学路や習い事の経路を事前に把握し、狙いうちするような高度な犯行モデルが確認されています。
また、最近では、スマホを使ってライブ配信中に背景から居場所を特定し、配信者が殺害される痛ましい事件が起こっています。
子どもを取り巻く環境は、かつてないほど複雑化しているのです。
都市部で気をつけるべき場所とは
1. 駅周辺

人の出入りが激しく、監視の目が分散しやすい駅は要注意。特に、出口がいくつもある駅や、駅構内が迷路のように複雑になっていると、自分が今どこにいるのかを把握しにくくなります。
よく利用する駅であれば、駅員さんがどこにいるのかを把握しておきましょう。特にエスカレーター、改札付近、ホームでは常に周囲に注意を払ってください。可能であれば、保護者や信頼できる大人と一緒に移動することが理想です。
2. 商業施設

商業施設では、空間が広く、多くのお客さんがいます。何かあればすぐに大声を出すか、制服を着た従業員に助けを求めることが大切です。知らない人には絶対についていかないように伝えましょう。
商業施設のトイレも要注意。子どもが小さいうちは一緒に行きましょう。子どもだけで誰でもトイレに入る時は、必ず中に誰もいないかを大人が確認します。子どもがある程度大きくなり、異性の場合であればさらに子どもだけで個室トイレに入るようになると思いますが、ちゃんと子どもの声が届く場所で待つようにします。
3. 公園・遊び場

広々としている公園でも、意外と死角となりやすい場所があります。遊具の陰、トイレ、植え込みなどに注意が必要。子どもには「なにか不自然」と感じたら、すぐに大声を出し、その場を離れるように教えてください。可能な限り、複数人で遊び、常に誰かの視界に入る位置にいるようにしましょう。見守っている親も、スマホに夢中になって子どもから目を離さないように気をつけて欲しいと思います。
4. 通学路

通学路は、毎日決まった時間帯に子どもが確実に通る場所として、不審者からは狙われやすい場所。可能な限り、集団登下校を心がけましょう。使い慣れた防犯ブザーを携帯し、GPSでの位置情報共有、定期的な経路の安全確認もしましょう。
防犯ブザーは日頃から鳴らす練習をしましょう。定期的に行うことで、万が一故障していても早く気づけると思います。
5. 人の多い場所

駅や商業施設以外にも、交通量の多い道路、マルシェイベント会場や遊園地など、都市部には混雑する場所があります。人混みの中では、人が死角になるので犯罪者は接近の機会を狙いやすくなります。人が多い場所へはなるべく子どもだけで行くことはやめましょう。
今回紹介した対策は、単なるルールではなく、子どもの「危険察知能力」を育てることを目的としています。子どもが自発的に想定外の状況にも対応できる力を養うことが、都市型犯罪から子どもを守る最大の武器だと思います。
具体的な防犯対策

では、子ども自身が自発的に危険予測ができるために、そして子どもの「直感」と「判断力」を養うには具体的に何をすれば良いのでしょうか。
1. ロールプレイング

ロールプレイングをすることで、危険な状況になった場合、どう対処するのが良いのか、何度も練習をすることで様々な対処法が身につくと考えています。
例えば、見知らぬ人に声をかけられた時の距離の取り方や、つきまとわれた際の逃げ方、冷静に不審者を観察して通報するコツなどが身につくでしょう。そして、110番通報をしたとき、緊急時に最低限「どこで・誰に・何をされた」のか、正確な情報を伝えられるよう何度も練習しましょう。
2. 状況判断をする

状況判断力を養うには、写真や動画を見ながら、危険な状況を瞬時に判断してみます。不自然な人の立ち振る舞いに気付けるか、犯罪の兆候を見つけられるかを親子で一緒に考えてみましょう。
シミュレーションを通じて、環境や人物から感じる不自然さを読み取り、迅速かつ的確な判断力が身につくと思います。
3. 緊急時の対応スキルを磨く

都市部では人混みや見知らぬ人が多いぶん、不審者と接触する機会も増えます。実際に危険な状況になった場合、どのように対処するのが良いのかも考えておきましょう。
周りに人がいるときは助けを求める、助けを求められない場合はとにかく逃げる、などあらかじめ想定しておくことも、いざという時の助けになります。街中は危険が多い場所ではあるものの、ただ怖がらせるのではなく、「何かおかしいと思ったら近くの大人に言うんだよ」と安心感を与えながら伝えるのがポイントです。
大切なのは、恐怖心を植え付けるのではなく、何かあったときに少しでも冷静に対処できる知識を身につけて欲しいと思います。
都市型犯罪から子どもを守る最新テクノロジー

都市型犯罪と呼ばれるものは、現実の街だけでなく、オンライン上でも発生しています。特に、インターネットを利用した犯罪は急増しており、特に子どもたちが狙われやすくなっています。最新のテクノロジーを活用した安全対策にはどのようなものがあるのか、気になる方も多いと思います。いくつか紹介します。
AIを活用した防犯アプリ

例えば、「SASENAI」のようなAI防犯アプリは、登下校中の子どもをターゲットにした犯罪を未然に防ぐことを目指しています。
スマホやデバイスの音声・映像・GPS情報をAIが分析。危険度をリアルタイムでスコアリングし、保護者への通知、警報、警察通報を同時に実行。従来の防犯システムを超える革新的な安全テクノロジーとなるよう、開発が進められています。
デジタル地図と犯罪情報の可視化

「ガッコム安全ナビ」のようなサービスは、自治体や警察が提供する犯罪情報をデジタル地図上にマッピングし、子どもや保護者が直感的に危険箇所を把握できるようにしています。不審者の目撃情報や事件発生地点がアイコンで表示されるため、都市部の複雑な環境でも安全なルートを選びやすくなります。
スマートデバイスによる監視と警告

子どもの位置をリアルタイムで追跡するGPS付きのウェアラブルデバイス(腕時計型端末など)は最近よく見かけるようになりました。これらは、子どもが安全なエリアから外れた場合に保護者に即座に通知を送る機能を備えており、誘拐や迷子防止にもなります。さらに、一部のデバイスは緊急時に子どもがボタンを押すことで助けを呼べる仕組みも搭載しています。
今回紹介したテクノロジーは数あるなかのほんの一部ですが、AI、IoT(モノのインターネット)、位置情報技術の進化を背景に、都市特有の課題—人口密度の高さ、情報過多、移動の複雑さ—に対応しています。特に、リアルタイム性と予測能力が強化され、犯罪の予防だけでなく、起きてしまった場合の迅速な対応も可能にしています。保護者や地域社会がこれらを活用することで、子どもたちを多様な都市型犯罪から守る安全網が構築されつつあります。
まとめ
・日頃から子どもに防犯意識を持たせる(ロールプレイング・シミュレーション)
・都市部のリスクを理解し、具体的な対策を講じる
・最新テクノロジーを活用し、安全ネットワークを強化する
子どもが被害に遭う痛ましい事件は、決して「他人事」ではありません。ネットやテレビのニュースでは目を覆いたくなるような事件も起きています。犯罪者は常に進化し、子どもを狙う手口は日々巧妙になっています。テクノロジーと犯罪心理の最新知識を常にアップデートし、家族と社会全体で子どもを守る意識が不可欠です。
個々の警戒と、コミュニティの連帯が、都市型犯罪と闘う最大の武器。一人ひとりが当事者意識を持ち、子どもの安全を社会全体で支える。それが、私たちにできる最も重要な防犯対策なのです。
-1.png)
安井かなえ
元警察官
小学生と幼稚園児までの3人の子どもの肝っ玉母ちゃん。警察庁外国語技能検定北京語上級を持つ。 交番勤務時代に少年の補導や保護者指導を経験後、刑事課の初動捜査班で事件現場に駆けつける刑事を経て、外事課では語学を活かし外国人への取り調べや犯罪捜査などを行う。 現在は、防犯セミナー講師として企業や市民向けに活動中。 好きな音楽はGLAY。