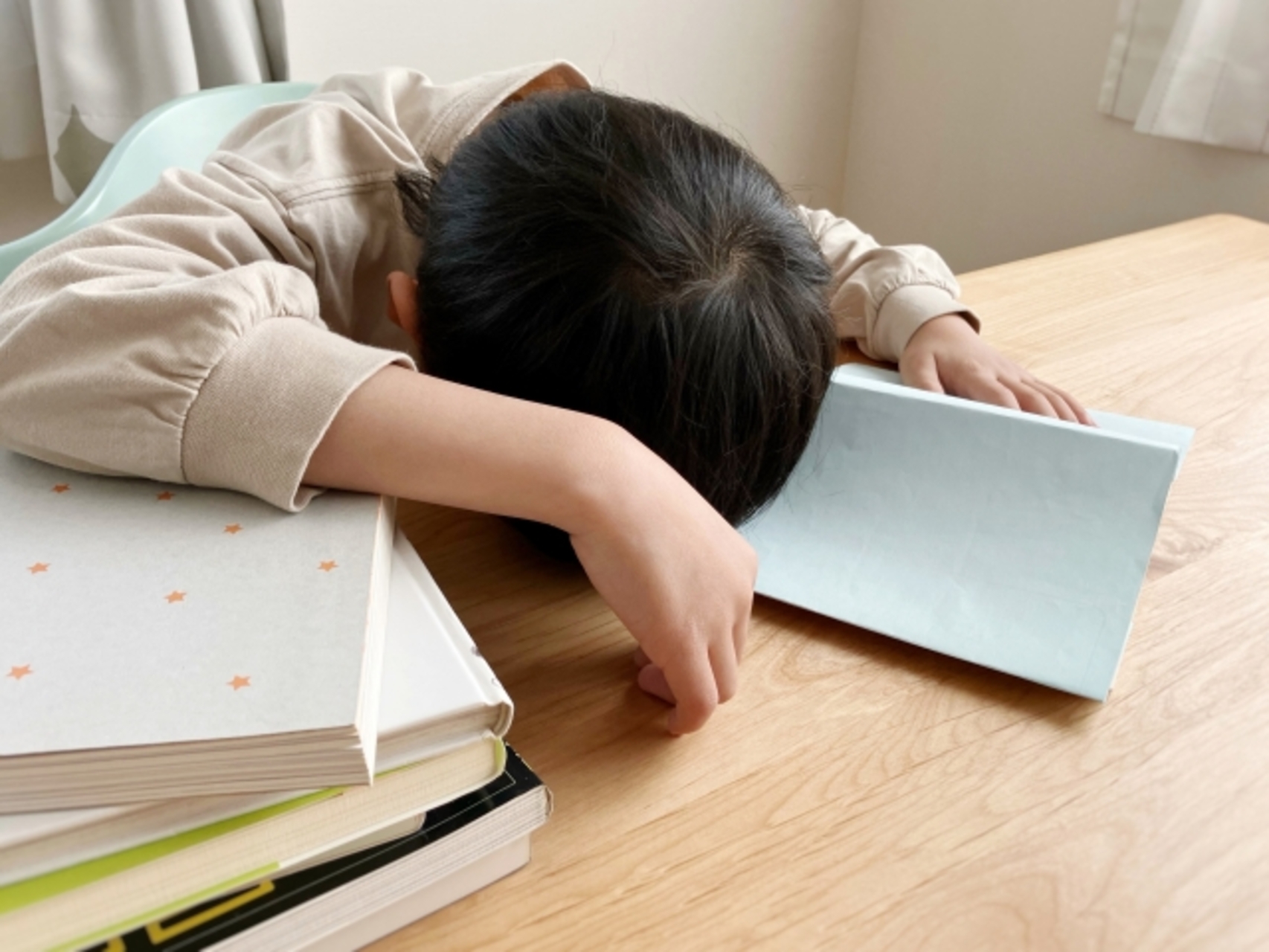小学生の塾選び|確認すべき6つのポイント
小学校3年生以降になると学習の強化や受験を意識し始めるため、塾に通う子どもが増えてきます。「うちの子もそろそろ塾に通わせた方がいいのかな…?」と悩む親御さんも多いのではないでしょうか。
しかし、塾といっても進学塾や補習塾、授業形式も集団・個別・オンラインとさまざま。小学生が塾へ通うとき、どんなポイントに気を付けて塾選びをすればよいのでしょうか。
今回は塾選びの際に確認すべき6つのポイントをお伝えします。
執筆 元教員 金島ちぐさ
目次
塾のスタイルや実績で選ぶ

中学受験のノウハウを持っている進学塾を選ぶのか、学校の授業をフォローしてくれる補習塾を選ぶのかは、一つ目の大きなポイントです。目的に合った塾を選びましょう。
進学塾
塾の前を通りかかると、窓に「○○中学校〇名合格!」と貼り出されていることがあります。このように進学実績を前面にアピールする塾は、いわゆる進学塾である可能性が高いでしょう。中学受験やその先の高校受験を見据え、よりレベルの高い内容を求めるのであれば進学塾がおすすめです。学習の内容はもちろん受験のノウハウも持っているので、志望校の決め方や勉強の進め方についても相談できるでしょう。
補習塾
学校でテストの点数が落ちてきている、勉強に苦手意識があって家庭ではなかなか取り組めないといった理由から塾を検討する場合は、進学塾ではなく補習塾がおすすめです。進学塾と補習塾に明確な区別があるわけではありませんが、塾のホームページやチラシ等を見るとその塾のスタイルが少し分かります。進学塾ではまず進学率や授業の質をアピールするのに対し、補習塾は勉強が苦手な子へのサポートや苦手教科の克服をアピールしています。塾選びの参考にしてください。
授業形式で選ぶ

塾のスタイルと同じように、授業形式も塾選びの大切なポイントです。同じ塾内で集団授業と個別授業の両方を行っていることもあるので、実際に塾へ見学や相談に出向くのがおすすめです。
集団授業
集団授業は、学校の授業と同じ授業方式です。クラスの人数は10~30人程度と幅があり、講師が前に立って授業を進めます。内容は、学校の予習として先取り学習をしたり、中学受験用の問題演習を行ったりと、塾によってさまざま。
授業料は集団授業の方が安価になる傾向があります。また、塾内で成績によるクラス分けが行われることもあり、ライバルの存在を感じながら勉強のモチベーションを維持しやすいメリットがあります。
一方で、学校の予習として取り組む場合でも、限られた時間で1週間分の内容を扱うためスピード感があり、宿題も多めになる傾向があります。勉強が苦手な子は少し負担に感じられるかもしれません。
個別授業
個別授業では、講師一人につき1~4人程度の子どもを担当します。講師が前に立って一斉に授業を行うのではなく、それぞれが自分のレベルに合った問題を解き、分からない部分について適宜質問をする方式です。苦手な教科や分からない単元に絞って取り組めるため、効率よく勉強を進めることができます。宿題の難易度や量についても、子ども本人や保護者の意向を汲んでもらえます。
一方で、講師一人あたりの子どもの人数が少ない分、授業料が高くなる傾向があります。また、ライバルの存在がないため、一人でコツコツと取り組むのが苦手な子どもはモチベーションを維持しづらくなる可能性があります。
オンライン授業
コロナ禍以降、オンライン授業を展開する塾も増えました。オンライン授業であれば住んでいる地域に縛られることなく塾探しができます。自宅で授業を受けられることから通塾の必要がなく、行き返りの心配や送迎の負担がないのもメリット。受験シーズンには避けたい感染症からも身を守ることができます。
一方で、パソコンやタブレットといった機材はもちろん、通信環境、カメラ、マイク、塾が指定するアプリケーションツールなどを準備する手間がかかります。講師の声がうまく聞き取れなかったり、資料がダウンロードできなかったりすると、せっかくの授業時間が無駄になってしまいます。また、対面式の授業でないことから、講師に質問することにハードルを感じる子どももいます。
講師の人数や雰囲気は要チェック

例えばいわゆる「カリスマ講師」と呼ばれるような有名講師であっても、お子さんとの相性はどうでしょうか。同じ授業でも、分かりやすいと感じるかどうかは人それぞれ異なります。質問のしやすさや親しみやすさなども含め、相性によって勉強の取り組み方や理解度も変わってくるので、ある程度講師の人数が多い塾を選んだ方がいいでしょう。また、万が一講師との相性が合わなかった場合に講師変更ができるのかどうかも事前に確認しておくと安心です。
周りからの評判は参考程度に
先ほどの内容と重なる部分がありますが、評判が良い塾や講師でも、我が子と相性が合うかどうかは分かりません。逆に評判があまり良くなくても子どもに合うケースもあります。塾の方針や雰囲気、取り組み方などがその人に合っていなかっただけで、自分たちとも絶対に合わないとは言い切れません。迷ったときに周りからの評判を参考にするのはいいのですが、大切なのは、自分たちの目で見極めること。最終的には見学や体験授業で確認しましょう。
模試や夏期講習などの追加オプションはくわしく確認を

「入会金無料」「紹介割引」などを使い、手ごろな価格をアピールする塾も少なくありません。もちろんこういった仕組みを上手く活用するのは良いことですが、長く通い続けるためには長期的な料金プランも知っておく必要があります。半年後から急に授業料が上がった、通常授業料が安いぶん夏期講習が高い、模試が強制参加だったなど、思わぬ出費につながるケースもあります。「こんなはずじゃなかったのに」とならないように気を付けましょう。
料金と立地から、通い続けることができるか最終判断
子ども自身が「ここなら頑張れそう」と思えるかどうか、料金が許容範囲かどうか、そして通塾にも問題がないかどうかが判断材料になります。子どもだけで通う場合は安全面の確認も必要です。見守りGPSを持たせるなどして、子どもが危険な目に合わないように気を配りたいですね。保護者が送迎する場合でも、長期的に無理なく送迎が可能かどうかをよく検討しましょう。
まとめ
・進学塾か補習塾か、目的に合わせた塾選びを
・授業料は長期的な目線でチェック
・無理なく安全に通塾できるかも大切に
以上、小学生の塾選びで確認したいポイントをご紹介しました。勉強を頑張るなら、ポジティブな気持ちで取り組みたいですよね。家庭の方針や子どもの意見を取り入れながら、ぴったりの塾を見つけてください。
-3.png)
金島ちぐさ
元教員
国立大学の学校教育学部にて、小学校教員と中高音楽教員の免許を取得。卒業後は小学校の正教員として勤務。結婚を機に退職し、現在は小学生2人を育てながら教育・子育てに関する情報を発信している。