
【入学準備】年長さんから勉強をスタートして、小学校生活をスムーズにスタートさせよう
入学準備で不安や疑問に感じやすいことの1つに、勉強が挙げられます。年長さんになるとひらがなを読める子も増えてきて、幼稚園や保育所でお手紙交換がブームになることも。年長のうちにひらがなの読み書きができないとダメ?数字はどれだけ分かればいいのか、今回は年長さんから取り組める勉強について解説します。
執筆 元教員 金島ちぐさ
目次
年長のうちに勉強をスタートする必要はある?

近年は早期教育に力を入れる保護者の方も多く、公文式や学研教室といった学習教室や、チャレンジやスマイルゼミといった通信教材などに幼児期から取り組んでいることも少なくありません。年長のうちに勉強をスタートした方がいいのか、不安になることもありますよね。
勉強面の準備を無理にする必要はなし!
結論から言うと、年長さんのうちから無理に勉強する必要はありません。小学校1年生では「ひらがなが一文字も読めない」「数字がひとつも分からない」ことを前提にカリキュラムが組まれています。まさに「一から」教えてもらえるので、過度に心配しなくて大丈夫。日常生活のなかで子どもが自然と数字や文字に興味をもてるように働きかけたり、子どもが興味をもったタイミングで少し勉強を始めてみたりするといいですね。
生活面の準備を優先して
勉強面は入学してから少しずつ頑張って追いつくことができますが、生活面は入学時にできていないと困る場面が出てくるかもしれません。
- あいさつや返事ができる
- 靴や衣服の着脱を一人でできる
- 持ち物を整理整頓し、大切に扱う
- 傘をさして歩ける
こういった生活面の準備は日常生活のなかで取り組めるものが多いので、練習しておくと安心ですので是非親子でやってみましょう。
ワクワクを高めるための勉強を
勉強に興味をもっていたり、どんな勉強をするのか気になっていたりするなら、そのワクワクを高めるための勉強に取り組みましょう。「勉強って、お兄さん・お姉さんみたいでカッコいい!」と感じている子どもも少なくないはず。「ちょっと小学生っぽいことやってみようか?」とうまく誘導して、えんぴつを持つところからスタートしましょう。
入学準備、ここを押さえれば、小学校生活をスムーズにスタートできる
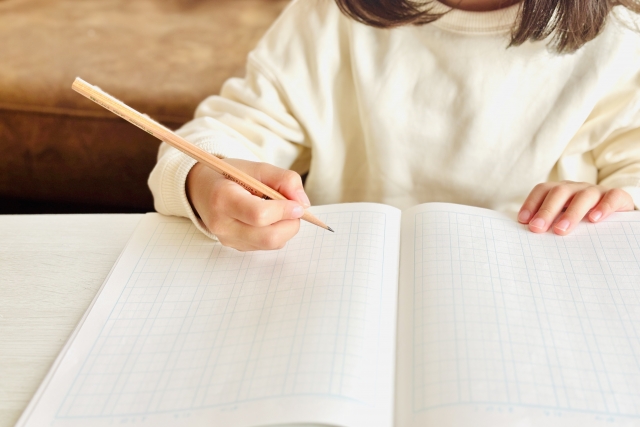
年長さんからの勉強は必ず必要なわけではありません。ただ子どもにやる気や興味があり、家庭で少しずつ勉強を始めようかなと思われる場合は、次の内容に取り組むのがおすすめです。
正しいえんぴつの持ち方
最初は、クレヨンなど太めの筆記具を「グー」の手で握りしめて使います。手の力が弱いうちはこれで問題ありません。年長さんになって手の力がつくと、色鉛筆やマーカーペンも使えるようになってきますので、このタイミングでいわゆる「えんぴつ持ち」ができるようにしましょう。小学校入学時点でえんぴつの持ち方が正しくない子どもは意外に多く、その持ち方で慣れてしまっていると矯正も難しくなります。家庭での勉強をスタートさせるなら、えんぴつの持ち方にも注意してみてくださいね。
ひらがなの読み
小学校に入学するとすぐにひらがなの勉強が始まります。入学後すぐに50音を学んだら、濁音や促音(っ)、拗音(ちゃ、ちゅ、ちょなど)と進み、夏休み前にはカタカナにも取り組み始めます。2学期の中盤からは漢字も始まるので、かなりのスピード感ですよね。年長のうちに少しでもひらがなが読めるようになっておくと、学校での勉強をスムーズにスタートできるでしょう。ドキドキワクワクの1年生。入学式の4月、授業が分かる!できる!という成功体験は、子どもにとっても大きな励みになります。
名前の書き
入学当初から持ち物やプリントに名前を書く機会があるので、自分の名前だけでも書けるようになっておくと安心です。書くことに興味があるなら、名前以外のひらがなに挑戦できるとより◎。先ほどもお伝えしたように、1年生の国語はとにかくスピード感があるので、無理のない範囲で先取り学習に取り組んでおきましょう。
10までの数字
数字の概念は、パッと理解できる子どもとなかなか理解できない子どもに分かれがちです。机に向かって勉強しなくとも、おもちゃを一列に並べてみたり、数を数えてみたりと、遊びの中で取り組みやすいのが算数のいいところ。時計を使って「10の針まで待ってね」という声掛けをすると、時計の勉強も同時にできますよ。
一番大切なのは、机に向かうことへの慣れ
年長さんの間は、嫌がる子どもに無理やり勉強させる必要はありません。ひらがなが読めなくても、数字が分からなくても、大丈夫。ただ、「机に向かう」ことすら難しいと、学校生活そのものが苦痛になってしまう危険があります。椅子に座って人の話を聞いたり、工作活動をしたりと、机に向かうことに慣れておくのは、大切なポイントになるでしょう。
小学校入学までに無理なく勉強をスタートするには?

親としては、少しでも先取り学習をしておいた方が安心ですよね。ただどの子どもも必ず勉強に興味があるわけではありません。無理なく勉強をスタートさせるために、次のポイントを押さえましょう。
短時間から取り組む
ノルマを課すような取り組み方や、完璧を求めるやり方は、年長さんの段階では必要ありません。もちろん毎日できなくてもいいので、できる日に短時間から取り組んでみましょう。繰り返しになりますが、入学前の勉強は必ずしなければならないものではありません。勉強のスタート段階で苦手意識をもってしまうのはもったいないので、子どもに寄り添ったペースで挑戦してみてください。
ポジティブな声かけをする
大切なのは子ども自身が「勉強って楽しいな!」「小学生になるのが楽しみだな!」と思えるようになること。ですので、「できないと小学生になれないよ」「できなかったら恥ずかしいよ」といったネガティブな声かけはNG。少しでも取り組めたことを認めたり、正解した問題を褒めたりして、ポジティブな雰囲気作りを心がけてください。
取り組みやすい教材を選ぶ
書店に行けば「入学準備ドリル」がたくさん並んでいます。ネットで無料配布されているプリントもありますし、通信教材も各種ありますので、取り組みやすいものを選びましょう。子どものやる気や予算と相談し、できれば一度実物を手に取ってみるのがおすすめです。市販のドリルであればネット購入ではなく書店で選ぶ、通信教材は無料サンプルを取り寄せるなど、工夫してくださいね。
まとめ
・年長さんから無理に勉強をしなくても大丈夫
・本人のやる気や興味に合わせてスタートしよう
・ポジティブな声かけで、勉強に対していいイメージを!
入学準備の一つとして考える、年長さんから始める勉強について考えました。
親としては少しでも早く勉強を始めた方が安心ですが、強要することで勉強に嫌なイメージがついてしまっては逆効果。子どもに寄り添った内容で、無理なくスタートしましょう!
.png)
金島ちぐさ
元教員
国立大学の学校教育学部にて、小学校教員と中高音楽教員の免許を取得。卒業後は小学校の正教員として勤務。結婚を機に退職し、現在は小学生2人を育てながら教育・子育てに関する情報を発信している。











