
夏休み明けにはここに注意。学習の遅れや登校渋りに気付いたらどうする?
夏休み明けは、いろんなつまずきに気付くタイミングです。学校へ行きたくない、いわゆる「登校渋り」をするようになったり、学校の勉強についていけなくなってしまったりと、思いもよらない問題が起こるかもしれません。
今回は、夏休み明けに注意したいポイントについて解説します。
執筆 元教員 金島ちぐさ
目次
2学期の始まり、小学生の夏休み明けで“学習の遅れ“に気付いたら?
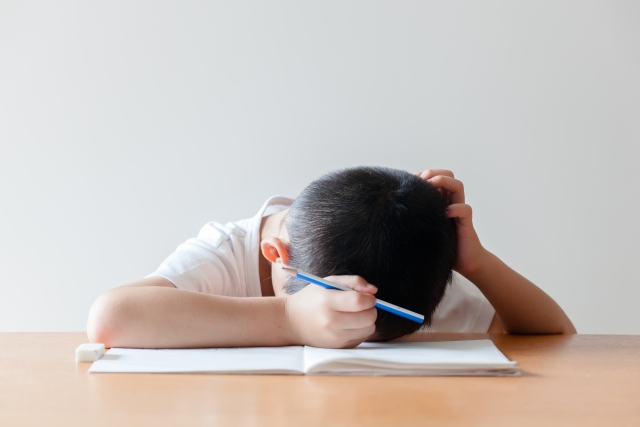
2学期の初めには、1学期の学習を振り返る内容の宿題や小テストなどがあります。このタイミングで、「うちの子、ちょっとつまずいているかも?」と気付く保護者の方も少なくありません。理解できていないのか、ただ忘れているだけなのか。お子さんの状態に合わせたサポートが大切です。
2学期に向けて、1学期の学習を“思い出す”サポートを
夏休みにも宿題は出ますが、40日ほどある夏休みを毎日しっかり勉強している子どもは少ないと思います。夏休み最後の1週間で慌てて宿題に取り組む子。反対に、宿題は早めに済ませておいて後半のんびり過ごした子。それぞれ「勉強をしなかった期間」がありますよね。
もちろん勉強のことを考えずにのびのび過ごす期間も大切ですし、それが夏休みの醍醐味でもあります。夏休み中に1学期の学習を忘れてしまったかもしれない場合は、早めに復習して思い出せるようにしておくといいですね。
2学期の学習は“レベルアップ”!つまずきやすい理由とは
どの学年も、1学期より2学期の方が学習内容も難しくなります。1年生は1学期で「10までのたしざん」をして、2学期では「10より大きい数のたしざん」に取り組みますし、3年生は1学期で「わり算」をして、2学期は「あまりのあるわり算」に取り組みます。
このように、1学年の間でも学習の積み重ねの上に新しい内容が入ってくるので、途中でつまずいてしまうことも。1学期の学習を振り返りながら、落ち着いて取り組むようにしたいですね。
予習?復習?子どもに合った方法でサポートしよう
小学生の間は基本的に、学校の授業で新しいことを学習し、宿題で復習する形を取ることが多いと思います。宿題だけでは学習がなかなか定着しないなという場合は、復習を増やすようにしましょう。市販のドリルや通信教材もよいですし、無料で印刷できるプリントを公開しているサイトもたくさんありますので、活用してみてください。
「学校の授業を聞いても分からない」という場合は、分からないことがストレスにつながったり、苦手意識がついたりしてしまいます。このときは予習に取り組むのがおすすめ。家で教科書を読んで次の学習内容を見ておくことで、安心して授業を聞くことができますよ。
夏休み明けに登校渋りをするようになったら?

2学期を前に、子どもの様子が「なんだかいつもと違うな」と感じることはありませんか?長期休暇の後に不安やそわそわ感を覚えることはよくありますが、そのまま「学校へ行きたくない」という気持ちにつながってしまうこともあります。
理由があるならまず受け止めよう
学習関係や友だち関係、先生との関係など、学校へ行きたくない理由があるならまずは受け止めましょう。「でも○○でしょ?」「○○だからいいんじゃない?」とすぐに解決させようとするのではなく、「それは悲しいね」「それが嫌なんだね」と、子どもの気持ちを受け止めることがポイントです。
はっきりとした理由がないことも
明確な理由がある場合は親としてもまだ対処しやすいのですが、登校渋りや不登校にははっきりとした理由がないことも多くあります。特に低学年では特に子ども自身が自分の気持ちや考えをうまく言語化できないため、結果として理由が分からないことも。親としては理由を知りたくなりますが、「どうして行きたくないの?」と何度も問い詰めるのは逆効果です。無理に言わせず、安心できる雰囲気を大切にしましょう。
無理に登校せず、エネルギーの充電期間を作ろう
いざ子どもの登校渋りに直面すると、「一度休ませたら癖になるのでは?」「このまま不登校になるのでは?」と不安になる気持ちもよく分かります。かといって、朝無理に家から出したり、学校へ連れていったりするのは子どもの心に大きな負担をかけてしまいます。心と体の準備が整うまで、エネルギーの充電期間を作ってみましょう。
生活リズムを整えて、できることから始めよう
学校を休んでいる間も、できるだけ生活リズムを崩さないことが大切です。朝決まった時間に起きる、家庭学習に取り組むなどをして、できる範囲で生活リズムを整えておきましょう。そもそも朝起きるのが難しい場合は心や体の不調が原因になっている場合がありますので、一度病院を受診してみるのもひとつの方法です。
登校のタイミングや方法は本人の気持ち優先で
子ども本人の気持ちが整わないまま無理に学校へ行こうとすると、また登校渋りが起こったり不登校を繰り返したりしてしまいます。午後から行く、別室登校をする、オンラインで授業に参加するなど、選択肢もいくつかありますので、学校側とも相談してみてください。
周りに助けを求めよう
子どもが登校渋りをするようになったり、そのまま不登校になったりすると、親の心にも負担がかかります。仕事の調整や子どもとの関わり方など、悩むことも多いですよね。両親や親せき、先生やスクールカウンセラー、自治体に設けられている相談窓口など、周りに助けを求めるようにしてください。家族だけで抱え込まないことも大切です。
まとめ
・予習または復習で、子どもの学習をサポートしよう
・登校渋りはまず子どもの気持ちを受け止めて
・お父さんお母さんも、周りに助けを求めよう
夏休み明けに注意したい子どもの変化について解説しました。
子ども自身も、親も、追い詰められないようにすることが大切です。周りに助けを求めたり、適切なサポートを受けたりしながら、子どもに寄り添うようにしましょう。
.png)
金島ちぐさ
元教員
国立大学の学校教育学部にて、小学校教員と中高音楽教員の免許を取得。卒業後は小学校の正教員として勤務。結婚を機に退職し、現在は小学生2人を育てながら教育・子育てに関する情報を発信している。











